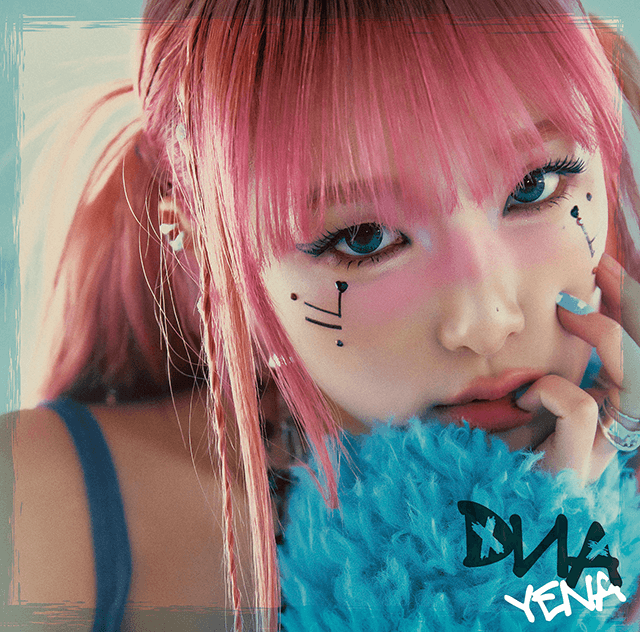ー お知らせ ー
フェイス・グループは、行動様式の変化や新たな価値観の定着を見据え、また多様で効率的な働き方の実現を
目的として、テレワークを常態とした勤務体制を導入しています。
音楽をはじめとする文化、芸術で、世界の人たちの人生を豊かに彩ることができるよう、当社グループは
「未来のエンタテインメント」の創造を目指し、 今後も 事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応してまいります。
なお、在宅勤務体制を実施していることから、弊社へのご連絡は引き続きホームページの
「お問い合わせ」フォームよりお願いいたします。
関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。